二宮金次郎は天明7年(1787)小田原市栢山に生まれ、安政3年(1856)に栃木県今市でなくなりました。二宮金次郎というとたいていの小学校の校庭に銅像がありましたので、殆どの日本人なら知っていると思いますが、生涯にどのようなことをし、どのような教えをしたかを知る人は少ないと思います。 二宮金次郎は天明7年(1787)に小田原市栢山の裕福な農家に生まれ、安政3年(1856)に栃木県今市で70歳で亡くなりました。生まれた頃は裕福でしたが、川の氾濫で田畑を失い、お父さんは金次郎が14歳で、お母さんは16歳の時に亡くなりました。 そこで叔父さんに預けられるのですが、ある夜 明かりをともして本を読んでいると叔父さんに怒られたのでした。「お前は誰のおかげで飯を食っているのだ。油がもったいない。」というのです。 金次郎は今度は空き地に菜種を植え、出来た菜種と油を交換して本を読むのですが、また叱られるのです。お前の時間は俺の時間だ。お百姓に学問はいらないというのです。それから始まったのが、薪を背負い歩きながら本を読む姿なのです。 やがて金次郎は叔父さんの家から独立し、実家の再興に取り掛かりました。そして勤勉と倹約に努め、24歳で以前のような裕福な家に再興しました。それを知った小田原藩士服部家に財政の建て直しを頼まれ、これも成功する事が出来ました。それが広まり今度は小田原藩の分家にあたる桜町領(栃木県二宮町)の再興を頼まれたりして、生涯に615の村々を立て直したといわれています。 金次郎は桜町領を再興するときに、武士の位を授けられ二宮尊徳となりました。このことは身分差別の象徴だと言う方もあると聞きましたが、二宮金次郎がそういう時代に生きていたということで、生涯にどういう業績を残したとか、どのようなものの見方考え方をしたかという事とは違うと思います。むしろどのようなことを人々に説いたかということが大事ではないかと思います。 まず 勤労、分度(倹)、推譲を人々に勧めました。 勤労とは 徳に報いるために働く、 分度とは 収入の範囲内で支出を定めること 推譲とは 勤労、分度をしてたまった物を将来のために残したり、人に及ぼしたりする事。 また「積小為大」「五常講」を人々に説きました。 積小為大とは小をつんで大と為すということです。 五常講とはお金の貸し借りの旋回の過程で、「仁」のこころをもってそれぞ れの分度を守り、多少余裕のある人から困っている人にお金を推譲し借りた 方は、「義」の心をもって正しく返済し、[礼」の心を持って恩に報いるため に冥加金を差し出すなど心を配って人に接し、「智」の心をもって借りた金 を運転し、「信」の心を持って約束を守る、すなわち「仁義礼智信」の「人 倫五常の道」を守ろうというのである。(童門冬二 「二宮金次郎」) |
||||||||||||||||||||||||||||||
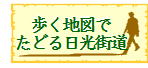 【リンクについて】 当サイトへのリンクは原則自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンク元のホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合などは、リンクの削除をお願いすることがあります。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. そのサイトの文章・画像、地図は著作戦で保護されていますので、無断での転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合は内容の加筆や削除はご遠慮下さい。また、ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||


