|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���߂ĕ����l�̂��߂� - �y �����n�}�ł��ǂ�����X�� �z���� �@�@��TOP�� ���Ώh����������Ƌ{�@�����w(�Ȗ،������s)�`���Ώh�`�������Ƌ{(�Ȗ،������s)�@2319m�@28�� ���Ώh�i�͂������キ�j �@�����X����21�Ԗڂ̏h�w�i�h�꒬�j�ł���B���݂̓Ȗ،������s���ΊE�G�B���Ώh�͍]�ˎ���ɉ��썑�s��S�ɂ������h�꒬�ł���B���Ƃ��Ɣ��Α��Ƃ������������������A���a3�N�i1617�N�j�ɓ���ƍN������R���J������Q�w������ƂȂ�Ɠ������Ƌ{�̖�O���Ƃ��đ傢�ɉh�����B���݂�JR�����w�̕ӂ�ɔ��Ώh�̖،˂��������B�����A���]�{�w�͌�K���A����{�w�͒����Β��ɂ���A�Q�w�҂͖{�w�ɓ��h���ē��Ƌ{���Q�w�����B �V��14�N�i1843�N�j�́w���������h����T���x�ɂ��A���Ώh(�͂������キ)�̋���2���A�h��176.728�A������5���A�l��985�l(�j516�l�A��469�l)�A�Ɛ�227���A�{�w2���A�e�{�w�Ȃ��A����19�����≮��1���A�h���l�n25�l�A25�D�ł������B �h��(���キ����)�Ƃ́@�_�앨�Ȃǂ�Ă̎�ꍂ�Ɋ��Z���āA���⒬�h��̋K�͂�\���������̂ł��B�P�ʂ͐E�l�E���E���E��(���Ⴍ)�ŁA1��10�l�A�A1�l��10���A1����10���ƂȂ�܂��B1����10�قƂȂ�܂��B1���͖�1.8?(�ꏡ�r1�{��)�ŁA1�͈ꏡ�r100�{���̗ʂƂȂ�܂��B�Ȃ��A1�U�͂����悻3�l5���̂��Ă����܂����B ��(���傤)�Ɗ�(����)�Ƃ́@���ƊԂ́A�����𑪂�Ƃ��̒P�ʂ̂��Ƃł��B1���͖�109.09m�ƂȂ�܂��B1����60�Ԃł��B1�Ԃ�6��(���Ⴍ)�ŁA��1.82m�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A���E�ԁE�ڂ͎���ɂ���Ă��������������قȂ�܂����B �{�w�E�e�{�w�E���ĂƂ́@����������قł��B�{�w�E�e�{�w�́A�Q�Ό��̑喼�Ⓔ�g�E�����Ƃ������M�l���h�����܂����B�{�w�����p�ł��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�����ɘe�{�w�����p����܂����B��ʗ��l���h�����闷�Ă�����܂��B���ẮA�H�����̏h���{�݂ł��B �≮��(�Ƃ���)�Ƃ́@�≮(�Ƃ���E�Ƃ��)�Ƃ������A���̏h��܂ŏ��p���l����n��p�ӂ�����A���p�̏o���҂̗��َ�z�ȂǁA�h��Ɩ�����舵���{�݂̂��Ƃ������܂��B �h���l�n(���キ���Ă����)�Ƃ́@�Q�Α喼���l�Ȃǂ��ʍs����Ƃ��ɁA�h��ŗp�ӂ���l��(�ɂ�) �Ɣn�̍ő吔�̂��Ƃł��B����Ȃ����͏���(��������)�Ƃ��āA���ӂ̑��X���璲�B���܂����B�{��50�l50�D�����蓖�Ă��Ă��܂������A����5�N(1808)��35�l35�D�ɕύX����܂����B �{�w���]�앺�q�i��K���j �{�w���쌹���i�����Β��j ������ ��� �\���� �ω��� ���{ �������� �m�ԓ� ����ʁ@��א_�� ��A��Ր_�@��q���� ��A�L�_�@����_(������N���J)�A�吙�_(�����O�\�N���J) ��A��Փ��@�O���\�ܓ� ��A�R�����v �@�@�Ó`�ɂ��Γ��Ђ͌��ۘZ�N(1218)�����R��\�Z�� ���s�ߐ� �@��א_�Ђ̒����������苫������ɂ���B �@�Ȃ��ނȂ��ގU��Ȃނ��Ƃ��N���v�� �@�@�����R�ɉԂ����ɂ��� �������� ��������� ���� �@�E���i�\���N(1640)�A�_���E�݂̔֗��_�i�����j���J���A�����Z�����̏Z���̒���Ƃ����J��B �@�E��N�A��������`�\���ɑ�Ղ����s�B �@�E��{���E�{��h�ɍʐF�̎Гa�́A�Ȗ،��������w��B �@�E�����ɑ�q��������B �����̂����������@�֗��␅ �@���S�]�N�O�����J�R�̑c������l�����̒n�ɐ���������ȗ��C���҂��_���ɋ������쐅�Ɠ`������B ���̐��͒j�̎R�n�̗N���ŁA���{�ł��ł������������Ƃ��Ē�]������B �����ω��� ���ω��� �����s�w�蕶�����@�j�� ���� �@���a�l�\�O�N�O���\�Z���w��(�w���\�܍�) �@���L�ҊǗ��� ������ЎO�c�R�r㻖{�� �@������l���������J�R(766)�������A���̔��Β���тɂ��n�߂Đl�Ƃ������A��l�̖��߂ɂ����̂��A�܂��͏�l�̍s�Ղ��]���閯�ԓ`�����͕s���ł��邪�A�u�������悤�Ȍ`��v�����̋N����ł���A��l�̖@���ɂ��₩����̂ł���B �@���̕t�߈�т͒������܂ł́u��{�v�ƌĂ�Ă������A�����R�̖�O���Ƃ��āu���Ώh�v�̖��̂ŌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A���a���犰�i�ɂ����Ă̓��Ƌ{���c���_�@�Ƃ��Ăł���A�]�ˌ܊X���̂ЂƂł�������X����O�h�w�̍ŏI�w�u���Ώh�v�ł���B �@�̂��A�̎��͂ɂ͍��݂��A���A���Đ_��������ĕی�̎肪�������Ă����B �@�����J�R�ɂ܂�閯�ԓ`���̌ÐւƂ��āA�܂��A�����ɂ������O���̔��B���������̂Ƃ��ĉ��l�������j�Ղł���B �����X���̋N�_�ɂ͂Ȃ�Ɛ����� ���Ώh �@�����X���̍ŏI�h�w�B�����h�Ƃ����悢�̂ɂƎv���l������ł��傤�B�������A���Ώh�Ƃ����܂��B����́A���̌`�������������āA����ɂ��Ȃ�Ŗ��Â���ꂽ����ł��B���݂����Ƃ�����������ɂ���܂��B���Β��͒�������̗։����̖�O���ŁA��A���A�����Β�����Ȃ��Ă��āA���ی��N(1644)�ɓ`�n�h�ɒ�߂��܂����B �@�{�w�͉����Β���2������܂������A�����ʉe���Ƃǂ߂Ă���̂́A�����s�����̓����Ɠ����͂����Α��ɂ��鍂��Ƃ����ŁA���̒�ɂ͔m�Ԃ̋�肪����܂��B�u���炽�ӂƖ̉��ł����̌��v�ƍ��܂ꂽ��́A�w���̍ד��x�̒��ɂ���u���炽�ӂƐt��t�̓��̌��v�ƒ�܂�O�̋�ł��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �����́u��v�̒� �@������͓������ς��Ƃ��ɂł��锖�����������グ�A��d�ɂ������グ�č���Ă���܂��B���ɂ͓����̖��������g���Ă���A�`������C�s�m�̂���ς����Ƃ��āA����Ă��܂����B�����s���ŁA���܂��܂Ȃ�Η�����H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �����ɂ������C�푈�@ �s�����ł̌o�܁t �@��C�푈�Ƃ́A���얋�ˑ̐����Ƃɑ��铝�ꍑ�Ƃ݂̍�����߂����āA�قȂ鐭���\�z���������������͂����˂����푈�ł���B �@�����ɂ������C�푈�̌o�߂͌c���l�N(�㌎���������E1868�N)�̋����{�����̐i�������A�������Ꝅ�̐i���A�ېV���{�R����h�O����̗��W�A�����{�咹�R�̐i���A���Ƌ{��_�̓����A�ېV���{�R�Ƌ����{�咹�R�̑Λ��A�����{�咹�R�̓����E�o�A�ېV���{�R�̐i�U�A�։����̓��k���s�A�ېV���{�R�̌R�������āA����m�����ɂ������̐ڎ��Ƃ����o�߂����ǂ邪�A�R��͋����{�咹�R�̐i������ېV���{�R�̐i�U�ł���B �@�����{�R�咹�\��́A�u�����R�̐_�_�ɂ��A�����̋`���������A�������v���v�ƗL�u���]�����Ђ����A�l����\�ܓ��A�]�˖��{�̐��n�����ɂ��ǂ���A�ېV���{�R�������Ȃ�A�����i�������j���Ă��Č��킷�����𐮂��A��͂��悢������ɂ������Ă����B��\�Z���ɂ͓��Ƌ{��_�̂̓����ɓ��ݐ�I�R�����Âւƈړ�����A����A�ېV���{�R�͓y���ˎm�_�ޏ����叫�Ƃ���\������s�܂Ői�R���A���߉߂��ɂ͍��s���A����\�����Ő퓬���n�܂����B�������A�����ɂ����钼�ڂ̏Փ˂͂����܂łŒ����܂ł͋y���A�[���ɂ͑咹�R��������E�o�����~���Ƃ���Z������z���킢���J��Ԃ��I�R�����Âւƌ��������B �@���̂悤�ɓ����́A�낤�����Đ��Ƃꂽ�̂ł��邪�A�_�ޏ��̐p����ю��̑m�������������A�����̊o��ō��s�̈ېV���{�R�Ɍ����������R�̑m�A�����@�����E���{�@�����̊���A���V���q���Â̑咹�ւ̐����A������s���̕ۑS��ȂǁA�����̐�l�����̓w�͂����茻�݂̔ɉh��z�����̂ł���B �@�@�����s����ψ��� �s��C�푈�W�̈�Ձt �@���b���Ԙa�d���Y�̕��i�����s�����E������j �@�����{�掵�A�������w�}��̏��Ԙa�d���Y�̕�A�c���l�N�l����\��������A���ˁi�p���j�̐킢�ŏd�����A�蓖�̂����Ȃ����S�A��\�Z�����s��䶔��ɕt����A����������ɖ������ꂽ�B �A������s���ᖡ���R�������q�̕�i�����s�����E������j �@������s�����ېV���{�R���̎p�����Ƃ�Ȃ��ōR������сA�i�U���Ă����[�l������A������E�o���A�����O�N�ېV���{�R�ɓ]������Ă��Ƃ�����_�䗴�Y�����ɘA�����A�撲���ɍ��������B �B������s���Ձi�����s���쒬�j �@���\�\�O�N�i1700�j����lj��~�ɓ�����s����n�݂��A�����l�N�����̓Ȗ؈ړ]�ɔ�����́B���̌�A�ۍW��̎������A�����z�e�����o�Č��݂͌Ð�d�H�̓����N���u�ƂȂ��Ă���B �C�{�{�ʏ��i�����s�R���j �@�c���l�N�[�l������A�i�U���Ă����ېV���{�R�͓�����s���̋ᖡ���ː����v��ɏo�}�����������̂��A�{�{�ʏ��ɂ����Ĉ����@�������{�@�����̉��ڂ��s��ꂽ�B���݂́A��r�R�_�АE���̏h�ɂƂȂ��Ă��邪�����̖ʉe���c���Ă���B �D�ېV���{�R�̏h���i�����s�R���j �@�T�q�@�ɂ͓y���˂���ь|�B�ˁA��Ɖ@�ɂ͕F���˂̏h���ɏ[�Ă�ꂽ�������h���͍]�ˎ���ɂ́A���ꂼ��̔˂̏h�]�ł���������ł���B �E���h�V�Ձi�����s�R���j �@�咹�R�̕������̕a�@�ɏ[�Ă��Ă����B�c���l�N�܌��\�O�������A���҂��̕��ɂ��Ď������B �F�_�ޏ������i�����s�㔫�Β��j �@����������~�������l�Ƃ��āA���a�l�N�Ɍ��Ă��A�����m�푈�ŋ��o���ꂽ�B���݂̓����́A���a�l�\��N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B �G��Ôˎm�`��E�L�̕��i�����s�㔫�Β��E�ω����j �@��Ôˎm�ő咹�R�Q�d�̊`��E�L�̕�A�c���l�N�l����\�O���A�F�s�{�̐킢�ŏd�����A��\�����A�������E�q����Ŏ��S�A�O�\�Z�ł������B �H�|�B�˕��l���̕��i�����s�㔫�Β��E�ω����j �@�|�B�ˁi�L�����j�̑��m�̕�A����ܘY���q���\�Z�A���Y�F�Y��\�O�A�n�ӑ��l��l�\�A�c�ӓ����V�i��\�̕�ł���B �I�|�B�˕������̕��i�����s�Ή����E�������{���e�j �@�|�p�ˁi�L�����j�����̑��m�̕�ŁA�ŔN���͑呺�L���Y�\���A�ŔN���͓n�Ӓn�l��l�\�A���̘Z�l�͂��������\�̎Ⴓ�ł������B �J�y���˕����f�����m�P�䐴���q��̕��i�����s�Ή����E�������\�����e�j �@�b�B�i�R�����j�Z�l�P�䐴���q��̕�A�E���ɂ��ˌ�Ƃ��ē����[�������A�߂炦���ď��Y���ꂽ�B�c���l�N�l����\����A��\�܍������B �K���厛�Ձi�����s����j �@�c���l�N�܌�����A���s��ꎟ�U���Ɏ��s������ÌR�́A���͂̎蔖�ȓ������U�������B�����ȑ����ł��������A���̖�A�F���˕��ɂ���ė��厛�y�сA������������哙���ē����ꂽ�B �L�咹���m�呐�ۏ��E�L�c�摾�Y�̕��i�����s�����E������Ձj �@�c���l�N�l����\�O���A�F�s�{�̐킢�Ő펀�����咹���m�呐�ۏ��E�L�c�摾�Y�̕�ŁA�㊯�̗��R�m������F�V�������Ă����̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s����ψ��� �@ �����]�����X ���얀�_�̓� �_�ޏ����� �@�_�ޏ��́A�u�_�����Ƃ����R�͎������v�̖����Œm���閾���̐����ƁB �@�����̏����Ɏ��R�����^����W�J���A���R�}�������B�y���i���m�j�o�g�B �@�������N(1868)��C�푈�̎��A�ނ͐V���{�R�̏��Ƃ��āA�����_�ɗ��Ă��������咹�\���̋����{�R��������Ў����������Ƃ�����B �@���̈⓿���]�����a�l�N�Ɍ������ꂽ���A�ŏ��̑��́A���풆�ɌR���ɒ������ꂽ�B���a�l��N�ɍČ��B�@�����ƁA�V�֍��b�̍�B �V�C��m���i�����t�j�� �@�V�C�͔�b�R�œV��@�̉��`������߂���A����ƂɎd���A�����R�̊ю�ƂȂ�B�����̓����͖L�b�G�g�Ɏ��̂�v������A�r�p�̋ɂ݂ɂ������B�ƍN���S���Ȃ�ƓV�C�͂��̈⌾����褋v�\�R����⍜������Ɉڂ�����Ƌ{�̑n���ɐs���������������̐l�ł���B �@�V�C�͊��i��\�N(1643)��Z���ő剝�������B���̓����́A�����o�g�̒����Ƒq����̍�B ���_�� �@ �[�������i�։��������j �@�`���u�R���̎��v�ɂ���悤�ɁA������l��s����J���n��Ȃ��ł��鎞�ɁA��C�̎ւ�����Ĉ�s���������[���剤�́u������V�v�̉��g�ł���A���̐̕����o�T�����߂ăC���h�Ɍ������������O������@����~�����Ƃ�����B���n���̐_�Ƃ����M����A�����сA�܂��A�M����u�����ɏ��v�̐M������B���Гa�́A���a�\�O�N�̍Č��B ���̋{ ���Y�� �@�_���߂��̘V���Q�̒��ŁA���̎����ł��傫���D�ꂽ�p�ł��邱�Ƃ���u���Y���v�ƌĂ�Ă���B �@����@��ܕS�\�N �@�����@�l�\�O���[�g�� �@�ڒʂ���́@�܁E���܃��[�g�� �@���a�O�\�N��A���H�g���v��̂��߁A���锰��ʂ̍ٔ��Œ��ڂ��W�߂��B �����؊�i��i���ʎj�Ձj �@�������j�Ƃ��̎q���M�̐e�q��オ�A��\�]�N���₵�ĎR���n��Ɠ��Ƌ{�֒ʂ�������X���A�䐬�X���A�ᕼ�g�X���A��Ð��X�������̉��O�\���L�����[�g���ɂ킽��A��\�����{�̐���A���A���Ƌ{�Ɋ�i�����B �@���̓��́A���̂��Ƃ��L�O���āA���M���c�����N�i1648�N�j4���Ɍ��Ă����̂ł���B���l�̔肪���ɎO��A�e�X���̓����_�̂̋����ƂɌ��Ă��u���v�Ƃ��Ă��B ���䗷�� ��������s���� �_�� �@����������R�����������ł��B�́A��r�R��ڎw���Ă���������l���A���̐�ɂԂ���n��Ȃ������Ƃ��A�_���ɋF�����Ƃ���A�[���剤������A�Ԃ��ւƐ��ւ����ɕς��ēn���Ă��ꂽ�Ƃ����܂��B���݁A�����̑�C���ŏI���A�ЂƂ���������P���Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ������l���� �@�_�ޏ��̓����ŗL���ȐV�֍��b���̓����ŁA�����s�s�����L�O���Č�������A���a30�N4��1���ɏ����������܂����B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �����R�։���(�O����) �@8���I���A�����J�R�̑c�A������l���n�������l�{�����ɋN�������B��C��~�m(���o��t)�Ȃǂ����R�����Ɠ`�����A�܂��A���c�����C�⌹�����Ȃǂ̕����̐M���W�߂āA�C������A�����R�O�Ќ����̐M�̒��S�Ƃ��ĉh���܂����B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �������Ƌ{ �@����ƍN�����J�邽�߂ɁA2�揫�R�G���������a3�N(1617)�N�ɑn���B���̌�A3�㏫�R�ƌ�����1�N5���������đ���C�����A���������܂����B���̌��z�ɂ���������p��56��8�痼�Ƃ����A���݂̂����ɂ���400���~�Ƃ����Ă��܂��B�z������͂��߂Ƃ���42�̌����͂��ׂāA������тɏd�v�������̎w����Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ������r�R�_�� �@�j�̎R(��r�R)�����_�̂Ƃ���s��ȋ��������_�Ђł��B8���I���ɁA������l���J�R���Ă�������R�M�̒��S�ƂȂ��Ă��܂����B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ��Q�@��_ �@����3�㏫�R�ƌ����̗�_�B�h�����Ă�܂Ȃ������c���ƍN�����J��ꂽ���Ƌ{�Ɋ��Y���悤�Ɍ��Ă��Ă���_�ŁA���Ƌ{�ɔ䂵�ė����������F�ʁE�������{����Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ����_�� �@�O�m11(820)�N�ɁA�O�@��t��C���_��̍~�����F�肵�A���_�̎p�����Č��������Ɠ`������_�ЂŁA��r�R�_�Ђ̕ʋ{�ł��B�Q���̓r���ɂ����̒���(�^���߂��̒���)��A�����т̍��ȂǂŐl�C������܂��B �����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �،˖�� ����L�����X ������ ���s�ߐ� ��א_�� ������� ���]�{�w �����O�� ���� �֗��␅ �ω��� ����{�w �V�C��m�� �_�ޏ� ���̋{ �_�� ����� ���ؒ� ������l �����q��l���S ���� �����؊�i�� ���Y�� �[������ ���� �����s �Ȗ،� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
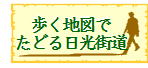 �y�����N�ɂ��āz ���T�C�g�ւ̃����N�͌������R�ł��B��L�����N�p�o�i�[�������p���������B �������A�����N���̃z�[���y�[�W�̓��e���@��������Ǒ��Ɉᔽ���Ă���ꍇ�Ȃǂ́A�����N�̍폜�����肢���邱�Ƃ�����܂��B �Ȃ��A���T�C�g�͗\���Ȃ��y�[�W�̕ύX�܂��͍폜���邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���炩���߂��������������B ���݃����N�́A�������@���炨�肢�������܂��B �y�Ɛӎ����z ���T�C�g���烊���N��ݒ肵�Ă���T�C�g�̓��e�́A�e�z�[���y�[�W�Ǘ��҂̐ӔC�ŊǗ��E�^�c����Ă�����̂ŁA ���ꂼ��̃����N�T�C�g�̌f����g�p�����ɏ]���ė��p�������B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�����n�}�ł��ǂ�����X���z http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp ����E����F���ɂȂ肽�� Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. ���̃T�C�g�̕��́E�摜�A�n�}�͒����ŕی삳��Ă��܂��̂ŁA���f�ł̓]�p�A�]�ڂ͂������������B �A���A�l�Ŏg�p����ꍇ�́A���͈̔͂ł͂���܂���B�������A��Ђ�c�̓��Ŏg�p����ꍇ�͘A���������B �����p�����ꍇ�͓��e�̉��M��폜�͂������������B�܂��A���ӌ���L�ړ��e�ɂ��Ă��ӌ���������������������B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



